アフェリエイト広告を利用しています
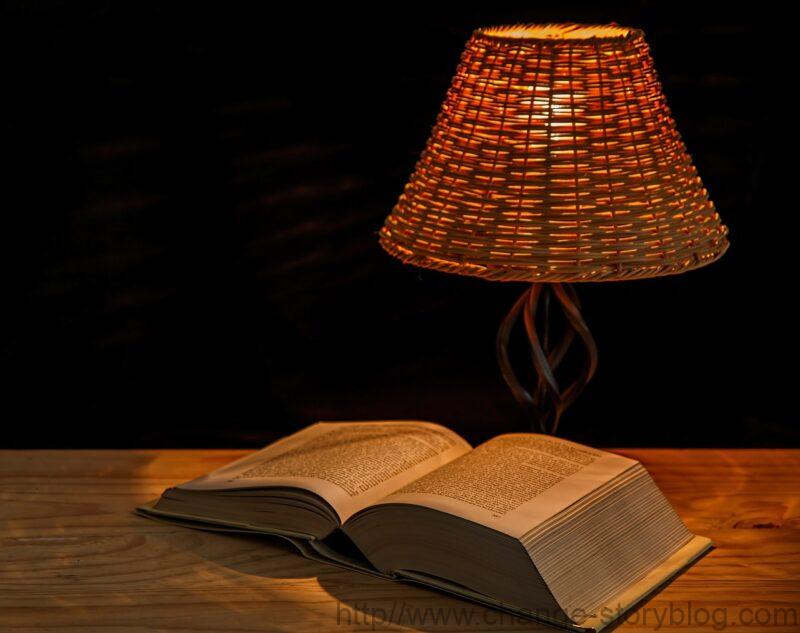
今回は、瀧森 古都さんの著書「悲しみの夜にカピバラが教えてくれた大切なこと」をご紹介します。
この作品は「親子のすれ違う愛情」や「本当の家族とは?」っていうのがテーマなんで、そういうのに弱い人や涙腺弱い人は外で読むの要注意ですよ!
親に対する理想や諦めを感じてきた人には、結局は「独りなんだ」「理解されないんだ」と思う気持ちが痛いほど分かる物語だと思います。
逆に自分が親になって分かる「子供に対する親の気持ち」「大事やと思うけど表現の仕方がわからない」っていう気持ちも理解できるから読んでて切なくなる場面もありました。
「親と子」って近いようで遠い...血が繋がってても理解できずにすれ違う人たちもいれば、血は繋がってなくてもホンマの親子のように理解し合える人たちもいる。
でも結局は他人も身内も関係なく、お互いを尊重して理解しようと努力していかないと、いい関係は築けないんだとこの本を読んで思いました。
今、親子関係で悩んでる人や、純粋な愛情に触れてみたい人、必見の感動ストーリーです!

この本をおすすめしたい人
・感動小説が好きな人
・「家族愛って何?」と思う人
・人の純粋な優しさに触れたい人
「悲しみの夜に」はこんなお話です
物語は夜の動物園に置き去りにされた少年が、発見されるところから始まります。カピバラ小屋に置き去りにされた少年。彼は母親に「すぐに迎えに来るからここで待っててね。」と言われていました。
どれだけ待っても少年の母親はやってきません。保護した園長が彼を引き取ることにします。カピバラが大好きな少年は、加比原 譲二(かぴばら じょうじ)と名付けられました。
やがて譲二は5歳の純粋な心を持ったまま大人になり、園長が校長として働く小学校に用務員として働き始めます。
すれ違い、傷つけあう親子関係に悩む登場人物たち。 譲二の純粋さは関わる人々に優しく寄り添いながら、心の闇を希望の光で満たしていきます。
「悲しみの夜に」登場人物
加比原 譲二…30年前に動物園のカピバラ小屋で置き去りにされる。小学校の用務員。
園長…動物園・児童養護施設の園長。施設退任後は小学校の校長
健太…小学校の生徒。
野口先生…健太の担任
美咲…健太の母。
早紀…小学校の生徒。剣道部の副部長。
近藤 正彦…早紀の叔父
明彦…早紀の父
「悲しみの夜に」見どころと心に響く名言

ここでは各章の見どころと
心に響く名言をご紹介します
第1章...名前のない男の子
譲二が動物園で発見されるところから始まり30年後、小学校の用務員として働いているところまでが書かれています。
園長さんが穣二に話を聞き、譲二が置き去りにされるまでの生活が分かってきます。読んでいると胸が苦しくなる場面もありますが、どんな親でも子供からしたら大好きな母親。子供が思う親への純粋な気持ちに1章目から泣かされます。
人の言葉を純粋に受け入れて、悪意や憎しみに気づかない譲二。譲二と同じ境遇の子供たちを想うと色々と考えさせられる章でした。
いくつになっても自分の名前すら書けない、計算することも、時計を読むことも、空気も読めない譲二。そんな園長が譲二に掛ける言葉です。
そのようなことができずとも、人は生きていける。計算が苦手なら、計算機を使えばいい。(中略)耳が聞こえないのであれば、ペンに言葉を託し、人と人は支え合って生きていくことができる。
人を思いやる気持ち、人を助けようと思う気持ち、人を許す気持ち、人を愛しいと思う気持ち、その気持ちを持ち続けていれば、人生は捨てたもんじゃない。
本書 第一章より
たとえ何かができなくても、代わりにできることを探せばいい。できないことよりも、その人ができることに目を向ける。
「誰かを思いやる気持ちや、助けようと思う気持ちを大事に生きていこう」と改めて思った言葉でした。
第2章...エコヒイキ
「エコヒイキ」あなたはこの言葉あまりいい言葉じゃないと思いますか?
この章では、小学校の生徒、健太君が譲二に100円をもらうところから始まります。「お金をもらうこと」や「借りること」子供のうちは「やったらダメ」と子供にも教えますよね。
健太君の担任野口先生も「エコヒイキになる。お金はあげちゃダメ!」と譲二に言います。健太君にはある事情があって譲二にもらった100円でノートを買っていました。
その理由を知った時、野口先生は「正しいことを教えるべき」か「人の優しさを褒めるべきか」悩みます。正論がいつも正しいわけじゃない。その正論の陰で泣く人や苦しむ人もいる。それを改めて考えさせられる話です。
その後、ある理由で心を閉ざしてしまっていた健太君のお母さんは、譲二にある言葉をかけられることで、本来の自分を思い出します。
抱きしめることに理由なんていらない。愛すること、愛されることに条件なんていらない。
本書 第二より
何かをするから愛してもらえる。何かの見返りに愛情をもらう。そんなことをしなくても愛情ってもらえるし、与えられる関係でいたいと心から思いました。
健太君のお母さんが元気になったことに喜ぶ譲二を見て、校長先生が感じたこと。
生きていると、人は迷子になることもある。自分がどこへ向かっているのかわからなくなり、立ち止まり、さまよい、自分の足元も出口も見えなくなる。
けれども、味方という名の愛の火をともすことで、人々は一歩前へ踏み出すことができるのかもしれない。何度でも…何度でも…
本書 第二章より
私も、誰かの「味方」でありたいと思いました。
第3章...勝利の女神
(注)この章は、後半ちょっと重いテーマになるので子供さんにおすすめする時は、先に内容を確認してからにした方がいいかもしれません。
小学校で用務員をしている譲二。ある出来事がきっかけで、剣道部の副部長、早紀ちゃんにいじめられるようになります。
それを解決するために譲二が取った行動で、早紀ちゃんは自分を取り戻していきます。その時、校長にこう言われます。
人間ってね、とても不思議な生き物なんだ。思い描いている方へ自然と寄っていく習性を持っているんだよ。(中略)
未来への道も同じ。毎日毎日想像している方向へ、自然と足が進むようにわたしたちはできているんだよ。
だから、楽しいこと、望むことをたくさん想像すれば、自然とその方向へ進む
本書 第三章より
耐えることが日常だった早紀ちゃんは、自分の望む自分とは何か、本来の自分とは何かを考えます。ありのままに生きる譲二に嫉妬していたことにも気づきます。
これを読んで、私もこれから先、楽しいと思えない時も、苦しみの中にいる時も、この言葉を思い出そうと思いました。
そして後半、早紀ちゃんのお父さんと、叔父の正彦の両親の死をめぐって物語は衝撃の展開を迎えます。正彦に校長が掛ける言葉です。
お兄さんは…あなたのお兄さんは…ただ愛されたかっただけかもしれない。たった一人でいいから、誰かに愛されたくて、認められたくて、(略)
本書 第三章より
人から愛情をもらい慣れていない人は、この感情が分かるかもしれない。小さいうちは親から、それが叶わないと分かると周囲の人から…「自分は愛されている」と分かるだけで人は強くなれるし、それだけで「自分はいてもいい存在なんだ」と感じられます。

物語は初めの優しいテンポから
急展開を迎えてクライマックスへ…
最後まで一気読みしてしまいます!
「悲しみの夜に」まとめ・感想
今回は、瀧森古都さんの著書「悲しみの夜にカピバラが教えてくれた大切なこと」をご紹介しました。
瀧森さんの本はほとんど読んでいるんですが、毎回感動します。今回のテーマが「親子の愛」だったので、自分の子供時代に考えていたことや言葉がたくさん出てきて、正直辛いところもありました。
今、親になって逆の立場からの気持ちも理解できるようになってからこの本を読むと、相手(親)にも思うことがあるのが理解できます。
「相手を思いやる心」「誰かを助けたい」と思う譲二の純粋な心に救われていく人たち…自分も誰かの「味方」であれたらいいなと思いました。
もし、今、苦しくてガマンしている人がいたら「自分は独りじゃない」と思ってほしい。そして「愛されたい」と思うことは決してわがままなんかじゃないと知って欲しい。
最後に、正彦が泣いている早紀の横で言った言葉です。
こいつはずっと我慢してきた。歯を食いしばって色んなことを我慢してきた。流さなきゃいけない涙も流さず、心の奥底に溜め込んできた。
そいつを全部流しきるんだ。心の奥底にへばりついている『へどろ』みたいな涙を流しきって、身体から全部泥を吐き出して、身軽になって、自分だけの自分らしい道を歩くんだ。
本書 第三章より
この本を読んだ、あなたの心が少しでも軽くなることを願っています。
30日間無料!「聴く」読書 Amazon Audibleはコチラ!
著者の紹介
瀧森 古都
1974年、千葉県市川市生まれ、2001年、作家事務所オフィス・トゥー・ワンに所属。放送作家として「奇跡体験アンビリバボー」など様々な番組の企画・構成・脚本を手掛ける。2006年、独立。
作家、コピーライターとして活動。現在、主に「感動」をテーマとした小説や童話を執筆。ペット看護士・ペットセラピストの資格を保持。
本書 著者略歴より抜粋





コメント